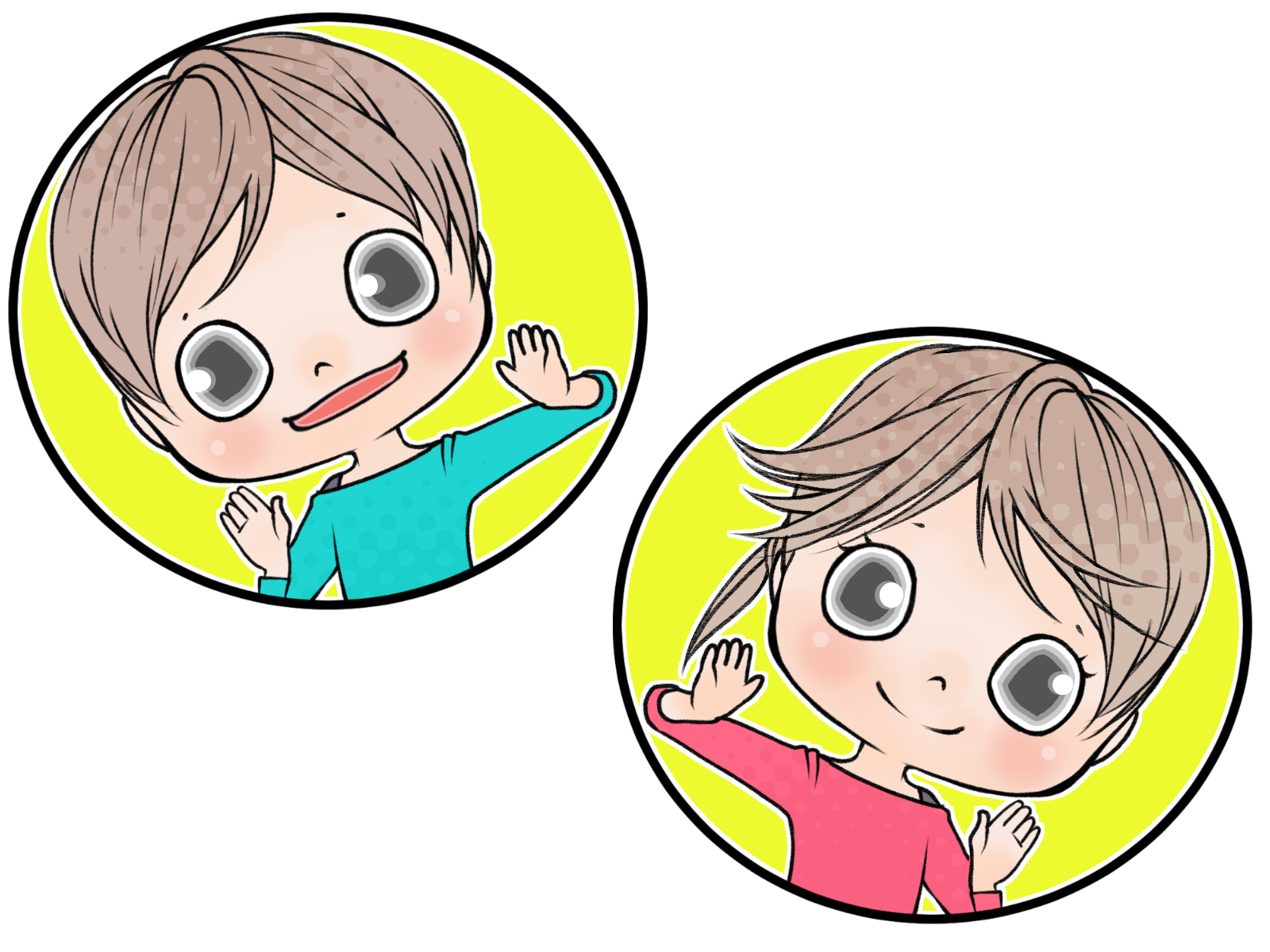バスクラリネットで高音の吹き方について、どうすれば高音をきれいに出すことができるのかお悩みの場合があると思います。
こちらの記事では、きれいな高音に近づく!という吹き方やポイントをご説明します。
そもそも、バスクラリネットの高音とは、クラリーノ音域をさします。
クラリーノ音域とは、クラリネットの名前の由来ともいわれる音域で、クラリネットの音域の中では一番美しい部分と言われている音域です。
それでは、さっそくそんな高音域を美しい音色に近づけるポイントを見ていきましょう。
目次
バスクラリネットの高音をきれいに出すための吹き方
 さて、バスクラリネットの練習を進める中で、皆さん壁にぶち当たっているのが、「高音域の吹き方」です。
さて、バスクラリネットの練習を進める中で、皆さん壁にぶち当たっているのが、「高音域の吹き方」です。
そもそもが低音域というイメージのあるバスクラリネットですが、どうすれば高音域もきれいに鳴らすことができるのでしょうか。
ここでは、バスクラリネットで高音をきれいに出すための方法を見ていきます。
楽器の調整
 まず前提として、高音域がきれいに出せないという人に多いのが、楽器の調整(セット)がうまくいっていないことがあります。
まず前提として、高音域がきれいに出せないという人に多いのが、楽器の調整(セット)がうまくいっていないことがあります。
具体的には、「バスクラリネット本体の上下管の接続がズレている」です。
こちらはセットする角度を変えて見るだけで解決する場合があるので、一度いいポジションを探ってみてください。
楽器本体の上下管がズレるというのは、バスクラの特徴の1つだったりします。
しかし、高音域がきれいに鳴らせない原因にもなり兼ねないので、セットは慎重に確実に行われることをオススメします。
<バスクラリネットのエンドピンの調整や種類について詳しくはこちら>
⇒バスクラリネットのエンドピン立奏用でおすすめは?ゴム製の評判も
アンブシュアのコツ
高音をキレイに出すにはアンブシュアにもコツがあります。2つのポイントを見ていきましょう。
B♭クラリネットよりは口を広く
バスクラリネットのアンブシュアは、基本的にはB管のクラリネットと変わりはありません。
しかしより下の歯を深めの位置にし、口の中の容積を大きくする必要があります。

バスクラを始めた人の中には、元々クラリネットを吹いていて、バスクラに転身した人や、曲によってバスクラに持ち替えて演奏される人もいるかもしれません。
クラリネットの場合は、高音域では口にある程度の緊張感が必要なのですが、
バスクラの場合は、適度な弛緩(下唇を少しゆるめる)が必要です。
また、それと同時に意識的に口の中を広げる事が大切になってきます。
クラリネットよりも管が長いため、たっぷりとした息で楽器を鳴らすよう心がけてみましょう。
高い音は口の中を狭く
また、低い音になればなるほど、のどを広げて口の中を大きく、
高音になればなるほど、下の歯をあまり深くしすぎず、口の中を狭くする必要があります。
アンブシュアのコツ
- B♭クラリネットよりは口を広く
- 低い音は口の中を大きく、高い音は狭く
と微妙な感覚に慣れていきたいですね。
次の項目では、どんな練習をすれば、高音域をきれいに鳴らすことができるようになるのか、練習のポイントをみていきましょう。
ロングトーンとレジスターキーの練習で息を一定に
日々の練習の中で、ロングトーンという練習を行いますよね。
ロングトーンは
「吹き出しから吹き終わりまで、まっすぐ安定して吹く」
が基本なので、無意味に8拍伸ばしたりせずに、
出したい音量や息のスピードで練習するようにしましょう。
ロングトーンを行なっている中で、
「ギャッ」や「ピッ」
というような音が出る時は、
- 「口が締まりすぎ」
- 「口が緩すぎ」
- 「息が強すぎ」
のいずれかに当てはまるはずです。
高音域のロングトーンでそんな音が出てしまう場合には、特に上記のような吹き方になっていることが考えられます。
そのため、そうなってしまう原因を探って見ましょう。
音がうまく出ない理由
- 口が締まりすぎ
- 口が緩すぎ
- 息が強すぎ
どんな息のスピードで、どれくらいの息の量があれば高音がきれいにあたるようになるか、ロングトーンで練習してみるのが、きれいな高音域を鳴らす近道かもしれません。
また、「高い音がうまく鳴らない」、「低い音と高い音の音色が違う」などの悩みを抱えている方には、レジスターキー(左手親指のキー)を使うロングトーンの練習を取り入れてみてはいかがでしょうか。
例えば、
「ミーーーシーーー」
「ファーーードーーー」
「ファ♯ーーード♯ーーー」
というように、
一番低い「ミ」を吹きながら、
レジスターキーを押して真ん中の「シ」、
低い「ファ」から真ん中の「ド」、
「ファ♯」から「ド♯」
この「低音から高音へ、レジスターキーを使って音を変える練習」は、
低音から高音まで、全て同じ息の量やスピード、アンブシュアで吹く練習となります。
高音を出すことに集中し、つい力んでしまいがちですが、この練習を続けることで、高音を鳴らせる息の量やスピードで、低音もコントロールできるようになるのです。
この練習のポイントは、
「息を一定量同じスピードで入れ、親指がレジスターキーを押したら音が変わった」
ができるようになることです。
これができるようになれば、高音域もきれいな音色が出せるようになるはずです。
ちなみにこのレジスターキーも、穴との間に変な隙間があるなど、きちんと閉まらなかったりすると、きれいな高音域にはならず、音程ミスなどの原因にもなりかねません。
一度確認されてみることをオススメします。
ロングトーンである程度高音域がきれいに鳴らすことができるようになった次は、高音域でもきれいなタンギングができるようになると、演奏できる曲の幅も広がりますよね。
高音域をきれいに鳴らすポイント
- ロングトーンで練習するのが、きれいな高音域を鳴らす近道
- 低音から高音へレジスターキ―を使って音を変える練習をする。(高音を鳴らす息の量やスピード、低音のコントロールだできる)
次の項目では、タンギングで音が割れないようにする吹き方について、舌とリードの位置を中心に説明します。
<バスクラリネットマウスピースのおすすめはこちら>
⇒バスクラリネットマウスピースのおすすめは?セルマー、ヴァンドレン、ヤマハの比較も
<バスクラリネット運指表で高音も分かりやすいのはこちら>
⇒バスクラリネットの運指表!高音・ロング管・低音分かりやすく
タンギングするときに音が割れないように舌とリードの位置に注意
バスクラリネットは弦バスのピチカートのような、頭打ちや後打ちが多いパートです。
そんな時、どうしてもタンギングがきつくなってしまい、音割れしてしまうこともあるのではないでしょうか。
例えば、「タッ・タッ・タッ・タッ」という楽譜であれば、音ごとに息を入れ直して吹くような吹き方ではいけません。
音を切る場合、舌でいちいち止めないようにします。
「タ」ではなく、「タン」と発音しながら、息を丸く前に出すようなイメージです。

その際に、リードのどこに舌のどの部分が接しているかがポイントで、
リードの先端近くに舌の先端がつくのが理想と言われています。
舌の真ん中がリードにつく人がいますが、タンキングが遅くなるため、これはやめたほうが無難です。
あくまでも先端がリードに触れるようにしましょう。
タンギングで高音をきれいに出すポイント
- 「タン」と発音して息を丸く前に出すようなイメージで
- リードの先端近くに舌の先端を付ける
B♭クラリネットと一緒に吹けるマウスピース
ちなみにですが、最近ではB♭クラリネットと同じアンブシュアでバスクラリネットも吹くことを可能にしてくれるマウスピースが発売されています。
バンドレンというメーカーのマウスピースで、「ブラックダイヤモンド BD5」という商品です。

少ない息でもまるく豊かな音質で、特に高音域で、深みのある演奏ができるマウスピースだそうです。
先ほども書きましたが、バスクラリネット奏者の中には、元々クラリネットを吹いていて転身された方もいらっしゃると思います。
吹き方の基本は同じかもしれませんが、クラリネットよりも息の量やスピードをコントロールする必要があり、難しく感じるかもしれません。
そんな方は上記のBD5というマウスピースを使用してみるのも良いかもしれませんね。値段は25,000円ほどで販売されています。
| メーカー | モデル | 価格 | 特徴 |
| バンドレン | BD5 | 約\25,000 | 少ない息でもまるく豊かな音
高音域は深みのある演奏ができる |
まとめ
さて、ここまでバスクラリネットで高音域を演奏する際の注意点をご紹介してきました。
ここまで見てきた内容をおさらいしておきましょう。
バスクラリネットで高音をキレイに出すポイント
- 高音になればなるほど下の歯をあまり深くしすぎず、口の中を狭くする必要あり
- 口の締めすぎには注意し、下唇はある程度緩めることが大切
- 高音域も低音域も安定した音を鳴らすには、息の量とスピードが大切
最初は合奏の編成の都合などで、クラリネットから転身された場合でも、
練習を続けていると、バスクラリネットの独特な魅力にハマる人が多いと言います。
実際、バスクラリネット奏者に聞くと、下記のような魅力があると言います。
バスクラリネットの魅力
- メロディから伴奏まで吹くことができる
- 独特の音色がする
- フォルム(特にベルの形)がかっこいい
あなたも数少ないバスクラリネットの名奏者を目指してみてはいかがでしょうか!
【バスクラリネット関連記事はこちらから】
⇒バスクラリネットマウスピースのおすすめは?セルマー、ヴァンドレン、ヤマハの比較も
⇒バスクラリネットのリードの厚さ・選び方・おすすめメーカーは? 育て方も知っておきたい